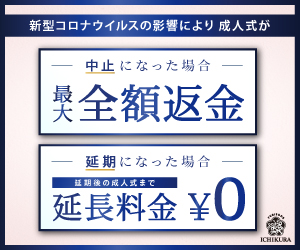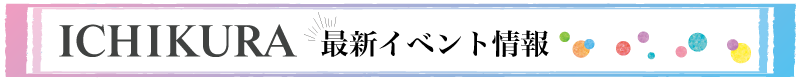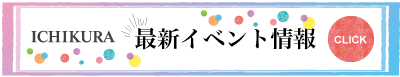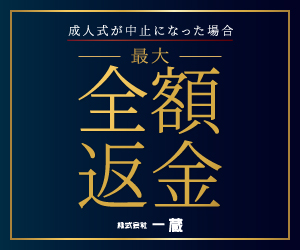「振袖の長襦袢はどのような役割がある?」「振袖の長襦袢を選ぶポイントは?」
「振袖の長襦袢の着付け方やお手入れ方法を知りたい!」
振袖を着る際に欠かせないアイテムの長襦袢ですが、特徴や役割についてご存知でない方は多いのではないでしょうか。
本記事では、長襦袢の特徴や役割について詳しく解説します。また振袖に合わせる長襦袢の選び方やお手入れ方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
長襦袢(ながじゅばん)とは?
長襦袢とは、着物の下につける肌着のことです。振袖を着用する際は長襦袢だけでなく、肌襦袢や半襦袢などのアイテムも欠かせません。また長襦袢に付いている半襟は顔まわりを華やかにするポイントにもなるため、選び方や素材にこだわる方も多くいます。
長襦袢の特徴
長襦袢は、「振袖(着物)」と「肌襦袢」の間に着用することが特徴です。長襦袢はツルツルとした滑りやすい生地で作られており、着物の滑りをよくして着崩れを予防してくれます。
長襦袢は着物のように長くつながったものや、上下で分かれているものがあります(二部式襦袢)。また袖部分がマジックテープになっていて取り外しが簡単にできるタイプのものもあり、季節に合わせて色や柄を付け替えできるため便利です。
長襦袢の役割
長襦袢の役割は以下の通りです。
- 振袖に汗や汚れが付くのを防ぐ
- 振袖の着崩れを予防できる
- 寒さ対策ができる
- 首元のおしゃれを楽しめる
長襦袢を振袖の下に着用することで、汗や汚れが付着するのを防げます。また滑りやすい生地を使用しているため振袖との摩擦が起こりにくく、着崩れの予防が可能です。さらに寒さ対策もできるため、寒さの厳しい成人式の際に役立ちます。
また長襦袢は振袖の襟元や袖口から見えるため、おしゃれとしての役割もあります。長襦袢につける半襟には色付きや無地、レース素材のものなどがあり、首まわりに華やかさを演出できます。
長襦袢の素材の種類
長襦袢に使用される素材は以下のとおりです。
- ポリエステルなどの化学繊維
- 正絹(シルク)
- 麻(リネン)
- ウール(モスリン)
近年の長襦袢は、お手入れのしやすいポリエステルなどの化学繊維で作られたものが増えてきました。天然素材のものよりも価格を抑えて購入でき、自宅の洗濯機で洗えるものもあります。ただし静電気が発生しやすいため、着用前に対策が必要です。
正絹(シルク)は肌触りが滑らかで、光沢感のある生地が特徴です。通気性・保温性に優れているため、夏は涼しく冬は暖かく過ごせます。
麻(リネン)は通気性がよく、汗をかいても肌に張り付かないのが特徴です。夏用の長襦袢として販売されています。ウール(モスリン)を使った長襦袢は保温性が高く、冬場でも暖かく過ごせます。
正絹・麻・ウールなどの天然素材は繊細なため、基本的に自宅の洗濯機では洗えません。購入する際はメンテナンス方法についても確認しましょう。
肌襦袢や半襦袢との違い
肌襦袢と半襦袢は、機能性に違いがあります。肌襦袢は、長襦袢の下に着用する和装肌着のことです。長襦袢が汚れないように、汗や皮脂を吸収する役割があります。
一方半襦袢は、肌襦袢と長襦袢の両方を兼ね備えた和装肌着のことです。肌襦袢のように汗や皮脂を吸収する役割を持ちつつ、長襦袢と同じ襟が付けられています。1枚で2つの役割を備えているため、夏の時期に着用する方が多いです。
長襦袢は振袖を着るときに必要?

結論からいうと、長襦袢がなくても振袖は着用できます。ただし長襦袢にはさまざまな役割があるため、着用するメリットのほうが大きいです。この章では長襦袢が必要である理由と、長襦袢がない場合の対応について解説します。
長襦袢は必要である
長襦袢は振袖を汗や皮脂などの汚れから守ったり、摩擦の発生を抑えて着崩れを防いだりする役割があるため必要です。また振袖を着用する成人式は、寒さの厳しい1月に行われるため、防寒対策が欠かせません。長襦袢には防寒の役割もあるため、振袖を着用する際には必要なアイテムだといえます。
ただし、夏場などで重ね着による暑さが気になることもあるでしょう。長襦袢を着用しない場合は、長襦袢と肌襦袢の機能を兼ね備えた「半襦袢」や「美容襟」などを使用するのがおすすめです。
美容襟とは、長襦袢の襟部分だけのアイテムです。「うそつき半襟」や「仕立て襟」ともいわれています。振袖は半襟が見えるのが必須のため、美容襟を肌襦袢の上に付けることで、半襟を見せることが可能です。
暑さなどの理由で長襦袢の着用を避けたい場合は、半襦袢や美容襟などの使用を検討してみてください。
長襦袢がない場合は購入もしくはレンタルしよう
振袖に合う長襦袢がない場合は、購入もしくはレンタルしましょう。振袖を取り扱っている店舗では、長襦袢の購入やレンタルが可能です。振袖によって袖丈のサイズが異なる場合が多いため、サイズに合う長襦袢があるか確認してください。
また振袖をレンタルする際は、レンタルプランの中に長襦袢が含まれている場合があります。店舗によってプラン内容が異なるため、契約する前にプランの詳細を確認しましょう。
長襦袢を選ぶ際のポイント

長襦袢を選ぶ際のポイントは以下の2つです。
- 振袖のサイズと合う長襦袢を選ぶ
- 着用シーンに合う長襦袢を選ぶ
それぞれのポイントについて詳しく紹介します。
振袖のサイズと合う長襦袢を選ぶ
長襦袢を選ぶ際は、必ず振袖のサイズと合うものを選びましょう。長襦袢は着物の種類によって、袖丈の長さが異なるからです。留袖用や訪問着用の長襦袢だと袖丈が足りず、動いたときに長襦袢の袖丈が飛び出してしまいます。
また振袖によって袖丈の長さが異なることもあるため、振袖用の長襦袢を手配しても合わない場合も多くあります。長襦袢を購入・レンタルする際は、必ず振袖の袖丈を測った上でサイズが合うものを選びましょう。
着用シーンに合う長襦袢を選ぶ
長襦袢を選ぶ際は、着用シーンに合う色や柄を選ぶこともポイントです。長襦袢は白や淡いピンクの色合いが多いですが、鮮やかな色や柄が入ったものもあります。結婚式などのフォーマルなシーンでは、白や淡いピンクの落ち着いた色合いの長襦袢がおすすめです。
一方成人式では、鮮やかな色や柄が入った長襦袢を着用しても問題ありません。袖口からちらっと見える色や柄がとてもおしゃれなので、ぜひ成人式の際に着用してみてください。
長襦袢を着用する際の手順とお手入れ方法

ここからは、長襦袢を着用する際の手順とお手入れの方法について紹介します。また長襦袢に半襟を縫い付ける方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
長襦袢を着用する際の手順
長襦袢を着用する際の手順は以下の通りです。
- 着る前に襟芯を通す
- 背中心を合わせる
- 胸紐は体の中心を避けて結ぶ
長襦袢を着る前に、まず襟芯を通しましょう。襟芯は、長襦袢に縫い付けてある半襟の内側に通します。とがっているほうを襟の外側に向けて、差し込んでください。
次に長襦袢を羽織り、襟先を合わせて胸の辺りを手で持ちます。長襦袢の背中心をそろえて、背縫いが体の中心になるように持ちましょう。衣紋は、こぶし1つ分くらい空くようにするとよいです。長襦袢の襟を右手で持っている下前に先に入れて、左手を上からかぶせます。クロスする位置は喉のくぼみ辺りにして、襟山はバストトップを通っているようにしてください。
最後に胸紐をアンダーバストに通して、体の中心を避けて結びましょう。結び終わったら背中のシワを取って、胸紐の下のシワを脇に寄せるようにして取ります。胸紐の緩みやシワを確認し、問題がなければ伊達締めをして完成です。
長襦袢に半襟を付ける方法
半襟とは長襦袢の襟に縫い付ける布のことで、振袖姿をきれいに見せるためのアイテムです。長襦袢に半襟を縫い付ける前に、しつけ糸・まち針・縫い針・アイロンを準備しましょう。
まず半襟を縁から2cmのところで折って、アイロンで軽く印を付けます。印を付けたところを長襦袢の背中心に合わせて、等間隔でまち針を打ってください。
次に半襟の端のほうから、長襦袢の外側の縫い付けを行います。外側(表側)が見えないため、大きめに縫っても問題ありません。縁から2~3mmのところを縫うとよいでしょう。半襟の端は、折り曲げて縫うようにしてください。半襟の真ん中から左へ、真ん中から右へと2cm、しつけ縫いを行います。
外側の縫い付けを終えたら、内側を縫います。アイロンを掛けてまち針を等間隔に刺して、印を付けると縫いやすいです。内側は縫い付けた糸が目立たないように、まつり縫いを行います。
外側・内側の縫い付けを終えたら、最後にアイロンを掛けて完成です。半襟がヨレないように、注意しながら作業を行いましょう。
長襦袢のお手入れ方法
長襦袢のお手入れ方法は、使用されている生地によって異なります。正絹やウールなどの生地は自宅で洗濯すると生地を傷めてしまうため、クリーニングに出すのが望ましいです。着用後は汚れている箇所をチェックした上で、早めにクリーニングに出しましょう。
また麻やポリエステルなどの化学繊維の生地は、自宅で洗濯できる場合もあります。もし長襦袢を自宅で洗濯する場合は、手洗いがおすすめです。手洗いをする際はおしゃれ着用の洗剤や洗面器、大きめのタオルを準備しましょう。長襦袢に付いている「洗濯表示マーク」を確認した上で、表示にしたがって洗濯を行ってください。
手洗いした後は、干す前にアイロンを掛けて生地を伸ばす必要があります。アイロンを低温に設定して、生地を引っ張りながら伸ばしましょう。アイロン後は半乾きの状態で、和装用ハンガーに掛けて陰に干してください。
振袖を着るときに必要なもの一式
振袖を着るときに必要な和装小物は以下の通りです。
- 長襦袢(ながじゅばん)
- 半襟(はんえり)
- 袋帯(ふくろおび)
- 帯揚げ(おびあげ)
- 帯締め(おびじめ)
- 重ね襟(かさねえり)
- 草履とバッグ
また上記だけでなく、着付けをする際に必要な小物も手配しなければなりません。着付けに必要な小物は以下の通りです。
- 和装用肌着(わそうようはだぎ)
- 襟心(えりしん)
- 腰紐(こしひも)
- 伊達締め(だてじめ)
- 帯枕(おびまくら)
- 前板(まえいた)
- コーリンベルト
- 補正用タオル
- 足袋(たび)
振袖を着るときは、上記の小物がすべて必要となります。自分で手配するには手間がかかるため、振袖と小物一式がセットになったプランを選ぶのがおすすめです。
一蔵の振袖レンタルプランでは、上記の小物一式がプランに含まれています。また振袖に合う小物をセレクトできるため、自分らしい振袖コーデを楽しめますよ。振袖レンタルプランに関する詳細は、以下の公式HPよりご確認ください。
まとめ
長襦袢は汗や皮脂を吸収し、振袖が汚れるのを防ぐ役割があります。また防寒対策や着崩れ防止の役割もあるため、振袖を着用する際は長襦袢を着用するのがおすすめです。振袖用の長襦袢を持っていない場合は、呉服店などで手配しましょう。
一蔵の振袖購入・レンタルプランでは、振袖に合わせた長襦袢を手配できます。また長襦袢だけでなく、振袖を着用する際に必要な小物一式がそろっているため、自分で手配する手間がかかりません。振袖に関するお困りごとやお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。